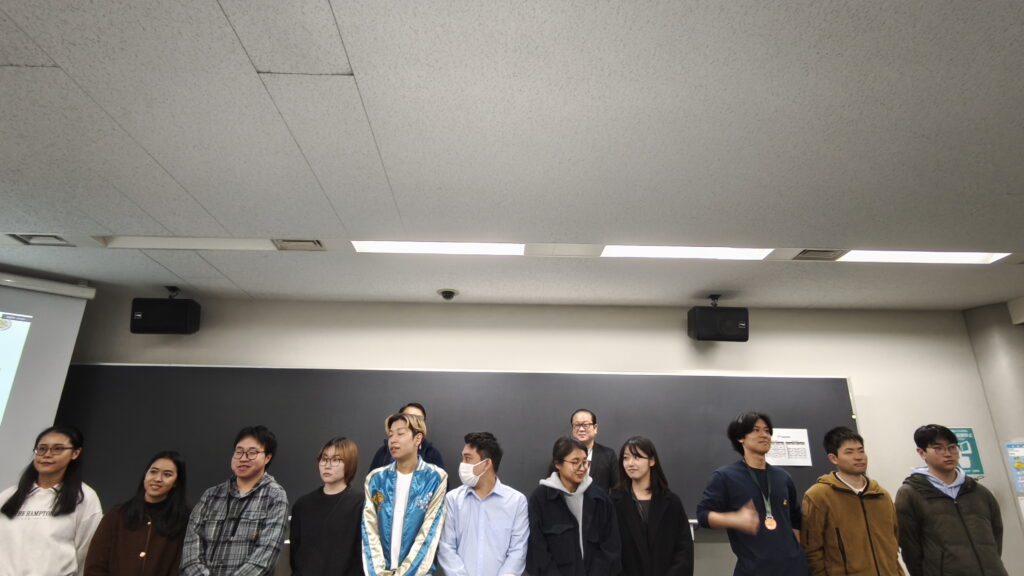芝浦工業大学豊洲キャンパスにおいて、「各国における土木工学の期待と役割」をテーマとしたグローバルPBLを実施しました。本プログラムは、土木工学が「市民工学」としての性質を持ち、国や地域の地理的条件、環境、文化に応じて異なる役割を果たすことを前提に、各国における土木工学の理想像や将来の姿を共に創造することを目的としています。
本プログラムには、芝浦工業大学の土木系学生48名(TAを含む)をはじめ、アジア各国の学生が参加しました。具体的には、アジア工科大学院(AIT)から22名、カセサート大学(KU)から42名、モンクット王工科大学トンブリー校(KMUTT)から20名、スラナリー工科大学(SUT)から5名、国立台湾大学(NTU)から11名の土木系学生が集結し、引率教職員を含む総勢165名の多国籍チームが編成されました。本プログラムでは、異なる国や文化的背景を持つ参加者が協働することにより、技術的知見の共有にとどまらず、異文化交流を深める機会も提供されました。
グローバルPBLの期間中、参加者には異文化体験の機会も設けられました。例えば、浴衣ワークショップでは、日本の伝統衣装を通じて国際交流が促進され、異文化理解が深まりました。このような文化交流は、技術的な議論だけでなく、円滑なコミュニケーションの構築にも寄与しました。
また、特別講演では、各国における土木工学の期待と役割に関する理解を深めるための講義が行われました。講演では、災害に強いインフラの設計や持続可能な都市づくりに向けた新たなアプローチが紹介され、特に気候変動に対応したインフラ整備の必要性が強調されました。これにより、学生たちは理論的な知識だけでなく、実務的な視点を学ぶ機会を得ることができました。
さらに、参加者は9つのグループに分かれ、「各国における土木工学の期待と役割」をテーマに討議を行いました。各グループでは、日本、タイ、台湾などの土木工学の必要性について議論し、それぞれの技術的知見を持ち寄ることで、多様な視点を統合することができました。この討議を通じて、各国の技術的相違を理解し、異なるアプローチを融合させる能力を養うことができました。
最終発表会では、各グループが討議の成果をもとに、独創的なアイデアや解決策を提案しました。特に、アジア全体のインフラの相互連携や災害対策の強化に関する提案が多く見られ、参加者全員がアジア地域のインフラ強靭性と持続可能性の重要性について理解を深める機会となりました。学生たちは、自国の技術や知識を他国の参加者と共有し、新たな学びを得ることで、国境を超えた協力の重要性を再認識しました。
今回のグローバルPBLは、技術的知識の共有にとどまらず、多国籍の参加者が協働し、国際的な課題に対する新たな視点を得るための貴重な機会となりました。参加者は、土木工学が果たすべき社会的役割を多角的に考察し、アジア地域におけるインフラの強靭性と持続可能性の重要性を再確認しました。この経験は、今後の学びやキャリアに活かされることが期待されます。